春日灯籠とは、神社や日本庭園などで古くから用いられてきた格式ある石灯籠です。
その存在感のある姿と、鹿や月の彫刻が施された火袋が特徴で、庭に静けさと品格を添えてくれます。
この記事では、春日灯籠の基本的な特徴や設置時の向き、初心者でも失敗しない選び方までをわかりやすく解説します。
「和の趣を大切にした庭づくりをしたい」「重厚な石灯籠を検討している」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 春日灯籠の歴史的背景と由来
- 特徴的な構造や彫刻の意味
- 設置時の向きや配置のポイント
- 雪見灯籠との違いや選び方の基準
春日灯籠とはどんな灯籠?

- 神社や寺に使われる由緒ある灯籠
- 重厚感ある形が庭を引き締める
- 雪見灯籠との違いは何か
神社や寺に使われる由緒ある灯籠

春日灯籠は、古くから神社や寺院に数多く設置されてきた、由緒ある石灯籠のひとつです。
その歴史は奈良時代にまでさかのぼり、特に春日大社をはじめとする神社の境内で多く見られることから、この名で呼ばれるようになりました。春日灯籠が他の灯籠と大きく異なるのは、その宗教的・文化的な背景に深く結びついている点にあります。
春日大社は、藤原氏によって創建された神社であり、神聖な場所として崇められてきました。そこに奉納されている灯籠は、単なる装飾や照明器具ではなく、「神々への捧げもの」「祈りの象徴」として大切に扱われてきたのです。特に、回廊や社殿を彩る灯籠は、信仰の証であり、代々の人々が願いを込めて奉納してきたものです。
また、灯籠そのものに彫刻された鹿や月、格子模様なども、春日大社の信仰と強く結びついています。鹿は神の使いとされ、神社の象徴的な存在として知られています。これにより、春日灯籠は見た目だけでなく、意味合いにおいても非常に重要な存在となっているのです。
つまり、春日灯籠は単なる石の彫刻ではなく、日本人の心に深く根づいた信仰と伝統が込められた存在であり、だからこそ神社や寺で広く用いられてきたと言えるでしょう。
重厚感ある形が庭を引き締める

春日灯籠が庭に与える印象の中でも、特に目を引くのがその「重厚感」です。高さのある竿、しっかりとした火袋、そして直線的な笠の組み合わせが、空間全体にどっしりとした落ち着きをもたらしてくれます。この力強い形状があることで、庭に一本芯が通ったような印象を与えることができるのです。
このように言うと、灯籠はあくまで装飾のひとつと思われがちですが、実際には庭の構成において「構造的な軸」の役割も果たします。たとえば、庭の片隅に配置された春日灯籠が視線を集め、庭の中心や奥行きにアクセントを加えることで、全体のバランスが整うのです。特に和風庭園では「非対称の美」が大切にされているため、あえて不均等に配置された春日灯籠が空間にリズムを生み出します。
一方で、春日灯籠は非常に存在感が強いため、設置場所やまわりの構成をよく考える必要があります。狭い庭に大きな灯籠を置いてしまうと、圧迫感が出てしまうこともあるため、サイズと配置には注意が必要です。
それでも、適切な位置に春日灯籠を据えることで、庭に「格式」「静けさ」「伝統」といった空気が自然と漂います。これが、他のアイテムでは得られない、春日灯籠ならではの価値なのです。
雪見灯籠との違いは何か

春日灯籠と雪見灯籠は、どちらも日本庭園に欠かせない石灯籠ですが、その特徴と役割は大きく異なります。それぞれの違いを理解することで、庭の演出にふさわしい灯籠を選びやすくなります。
まず形状の違いですが、春日灯籠は「縦に長く、直線的」であるのに対し、雪見灯籠は「横に広がった丸みのある形」をしています。春日灯籠は高い位置に火袋を持ち、神社や寺院の参道や境内によく似合う厳かな佇まいが特徴です。一方、雪見灯籠は笠が大きく、水辺に配置されることが多いため、視線を低い位置に誘導する柔らかな印象を与えます。
設置する場面も異なります。春日灯籠は、庭の正面や奥など視線を集める位置に据えることで、「構成の中心」になるアイテムです。対して雪見灯籠は、池のそばや庭の縁に置くことで、風情や遊び心を感じさせる演出に向いています。
また、象徴性にも違いがあります。春日灯籠は鹿や月などの彫刻が施されており、宗教的・精神的な意味合いが強く込められています。それに対して、雪見灯籠は季節感や自然との調和を重視したデザインが多く、やや装飾性に寄った側面が見られます。このように、春日灯籠は「伝統・格式・荘厳さ」を演出するのに適しており、雪見灯籠は「柔らかさ・親しみやすさ・風情」を表現するのに向いていると考えると、それぞれの使い分けがしやすくなります。
春日灯籠を置く向きと場所とは?

- 火袋の窓の方向に注意しよう
- 庭に合う配置パターンを紹介
- 和モダンな庭にも似合う灯籠
火袋の窓の方向に注意しよう

春日灯籠を設置する際には、火袋の窓の向きに特に注意が必要です。火袋には開口部があり、その部分から灯りが漏れる構造になっています。この開口部をどこに向けるかで、灯籠全体の印象や庭の雰囲気が大きく変わってくるため、ただ何となく置くのではなく、意図を持って向きを決めることが大切です。
多くの場合、火袋の窓は“見せたい方向”に向けるのが基本とされています。たとえば、玄関や飛び石の先、通路の正面など、人の視線が自然と向かう場所に窓を向けることで、灯籠の魅力をより引き立てることができます。火袋の中に光を入れる場合も、開口部が目に入ることで視覚的なアクセントとなり、夜間のライトアップにも効果的です。
一方で、あえて開口部を横にずらすことで、控えめで落ち着いた雰囲気を演出することも可能です。特に庭全体の中で、灯籠が主役ではなく“脇役”として機能する場面では、このような配置が効果的です。
また、火袋に彫刻が施されている場合、その模様の配置も向きを決める際の重要な判断材料になります。鹿や月の彫刻を正面に向けたいのか、それとも控えめに見せたいのかによって、設置方向は変わってくるでしょう。
このように、火袋の窓の向きひとつで、庭全体の印象は大きく変化します。設置前に、どの方向から灯籠を見ることが多いかをイメージしておくと、後悔のない配置がしやすくなります。
庭に合う配置パターンを紹介

春日灯籠は、その存在感と格式あるデザインから、庭の印象を大きく左右するアイテムのひとつです。置き場所を間違えると圧迫感が出たり、逆にその良さが活かしきれなかったりするため、庭の広さや構成に応じた配置パターンを知っておくことはとても重要です。
もっとも王道の配置は、アプローチの脇や玄関前です。来客が必ず目にする場所に据えることで、第一印象に「和」の落ち着きと品格を与えることができます。この場合、火袋の窓を通路側に向けることで、視覚的な焦点が自然に灯籠に集まり、庭の格を一段高めてくれます。
また、飛び石の終点や奥行きのある場所に設置する方法も効果的です。視線の誘導役として春日灯籠を使うことで、庭の“奥行き”や“静けさ”を演出できます。特に苔や砂利を組み合わせると、より落ち着いた雰囲気になります。
一方、中庭や坪庭の隅に対角線上に置くという配置もおすすめです。限られたスペースでも春日灯籠の重厚感を活かしやすく、庭に奥行きを感じさせることができます。目線のずらし方を工夫することで、空間に動きとリズムが生まれ、より洗練された印象に仕上がります。
もちろん、配置の際は周囲の植栽や塀、石材とのバランスも忘れてはいけません。大きな春日灯籠を狭い空間に無理に置いてしまうと、全体が窮屈に見えてしまうこともあるため、設置前に庭全体を俯瞰して見取り図を描くような気持ちで考えると失敗しにくくなります。
和モダンな庭にも似合う灯籠

春日灯籠は、古典的な和風庭園にしか合わないと思われがちですが、実は和モダンな庭にもよくなじむアイテムです。その理由は、春日灯籠が持つ「直線的でシンプルな構造」にあります。過剰な装飾がないため、モダンな空間にも違和感なく溶け込むのです。
特に、白を基調とした外壁や、コンクリート調の無機質な背景に合わせることで、春日灯籠の石の質感や彫刻が引き立ちます。このように対比を活かすことで、伝統と現代が融合した“和モダン”らしい空気を演出することができます。
また、和モダンの庭では照明計画も重要です。春日灯籠にLED照明やソーラーライトを組み込むことで、夜間には幻想的な光の演出が可能になります。柔らかな灯りが石材の彫刻を浮かび上がらせ、昼とは異なる表情を見せてくれます。
デザイン面だけでなく、**意味合いの面でも和モダン庭に適しています。**春日灯籠は、神聖さや祈りの象徴としての役割を持つため、シンプルで静かな空間と非常に相性がよいのです。無駄な装飾を省いた現代的な庭においても、ひとつ置くだけで場の空気に深みが加わります。ただし、春日灯籠の存在感はかなり強いため、配置の際は周囲をあまりごちゃごちゃさせず、抜け感や余白を大切にすることがポイントです。植栽を抑えめにして、灯籠そのものを“主役”として見せるように意識すると、より洗練された和モダン空間に仕上がります。
春日灯籠の価格と選び方のコツ!

- 庭に合う配置パターンを紹介
- 和モダンな庭にも似合う灯籠
- 価格の相場とその理由とは
価格の相場とその理由とは
春日灯籠の価格は、一般的に3万円〜30万円前後が主な相場となっています。もちろん、素材や仕上げ、サイズによって大きな差があるため、まずは相場の幅を理解しておくことが大切です。
比較的安価なものは、モルタルや中国産の石材を使った機械加工の灯籠で、3万円未満から購入することができます。この価格帯の製品は軽量で設置しやすい反面、彫刻が浅かったり、デザインの精度が低いことが多いため、外観の繊細さや耐久性にはやや不安が残る場合があります。
一方、10万円を超えるような春日灯籠は、御影石などの高品質な天然石を使用し、熟練の職人によって手彫りされた製品が中心です。彫刻の深さや火袋の細工、全体のバランスにおいて圧倒的な美しさと重厚感があり、格式のある和風庭園にふさわしい存在感を放ちます。
このように価格が大きく変動する理由は、使用される石の種類や産地、加工の方法、彫刻の細かさなど複数の要素が組み合わさっているからです。また、国産か海外製かでも価格に差が出ます。国産の手彫り製品は希少性が高いため、相場が高くなりやすい傾向にあります。
庭のスタイルや設置環境に合わせて、どの価格帯がふさわしいかを見極めることが、後悔のない選び方につながります。
素材とサイズで変わる価格帯

春日灯籠の価格を決める最大の要素は、使用されている素材とサイズです。見た目が似ていても、石の質や加工方法が異なるだけで価格は倍以上変わることも珍しくありません。
まず素材についてですが、もっともよく使われるのが「御影石(みかげいし)」です。御影石は非常に硬く、風化しにくいため、屋外設置に適した高級石材として知られています。国産の白御影石は光沢や色合いが美しく、価格も比較的高くなります。一方、中国産やベトナム産の御影石は価格が抑えられていますが、質感や耐久性でやや差が出ることがあります。
次にサイズですが、春日灯籠は高さ60cmほどの小型サイズから、2mを超える大型タイプまで幅広く存在します。**当然ながらサイズが大きくなるほど材料費と加工費が増えるため、価格も高くなります。**また、大型の灯籠は運搬・設置にも手間がかかるため、追加のコストも考慮する必要があります。
さらに、火袋に彫刻が施されている場合、その彫刻の種類や深さによっても価格が変動します。たとえば、鹿や月、格子模様などがしっかり彫られているタイプは、その分手間がかかるため、価格も高めに設定されていることが多いです。
同じ「春日灯籠」というカテゴリでも、素材やサイズの違いによって、その価値と価格帯は大きく変わるのです。
初心者におすすめの選び方

初めて春日灯籠を購入する方にとっては、どのタイプを選べばよいのか迷ってしまうことも多いでしょう。価格やサイズ、設置方法など考えるべきポイントが多いため、いきなり高価なものを選ぶのは少しハードルが高く感じるかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、「3万円未満の軽量モデル」から始める方法です。この価格帯の灯籠は樹脂製やモルタル製で作られていることが多く、重さも軽く設置が比較的簡単です。庭に据えたときのイメージをつかみたい方や、まずは試してみたいという方にとっては、手軽な選択肢となります。
また、選ぶ際は設置する庭の広さやデザインとの調和を意識しましょう。広い和風庭園であれば高さ1m以上の本格石灯籠が映えますが、狭いスペースや坪庭であれば60〜80cm程度のコンパクトな灯籠の方が自然に馴染みます。大きさのバランスは、庭全体の印象に直結するため重要なポイントです。
さらに、火袋の彫刻が施されているかどうかもチェックしてみてください。鹿や月などの模様があると、それだけで雰囲気が増し、春日灯籠ならではの美しさが際立ちます。ただし、彫刻入りの製品はやや価格が上がる傾向があるため、予算との兼ね合いで検討しましょう。最初の一基は“実用と雰囲気を兼ね備えたもの”を選び、設置してから「もっと本格的な灯籠が欲しい」と感じたら、次にグレードアップするという段階的な進め方もおすすめです。これにより、失敗を防ぎながら理想の庭づくりに近づくことができます。
灯籠のおすすめ商品紹介
初めて購入を検討されている初心者の方には手軽におけるソーラータイプの灯籠を、本格的な春日灯篭をお探し方には高級石材を使用した重厚感がある本物の春日灯篭を紹介していきます。楽天市場でも高級灯篭が販売されていますのでご参考にしてください。
●初心者にぴったりな和風ガーデン灯籠
初めて庭に灯籠を置いてみたいという方におすすめなのが、扱いやすくて設置も簡単な和風ガーデン灯籠です。石灯籠のような見た目を保ちつつ、素材は軽量で移動もラクラク。ソーラー充電式のものを選べば、配線不要で手間もかかりません。
和の雰囲気を気軽に取り入れたい方にぴったりのアイテムです。
【おすすめ】ソーラー式雪見灯籠(自動点灯・屋外用)
価格:4,000円〜5,000円台(Amazon)
春日灯籠に近い雰囲気を持つ、雪見型のソーラー式灯籠です。
石風の質感と丸笠の形状が庭に和の趣を添えてくれます。
電源不要のソーラー式で、夜には自動で点灯するため、手軽に設置できます。
この価格帯では春日灯籠そのものは見つかりにくいため、
まずはこうした雪見型の灯籠から雰囲気を楽しむのも選択肢のひとつです。
ソーラー式和風灯籠ライト(自動点灯)
価格:7,532円(税込/楽天)
伝統的な雪見灯籠の形をモチーフにした、屋外用ソーラーライトです。
石風の質感と丸笠のフォルムが特徴で、庭に品のある和のアクセントを添えます。
電源不要で、日中に充電→夜間は自動点灯。配線いらずで設置も簡単なので、DIY初心者の方にもおすすめです。
●格式と重厚感を備えた本格派春日灯籠
日本庭園や神社仏閣の空気をそのまま庭に持ち込める、伝統技術で作られた本格的な春日灯籠。
御影石などの天然石を使い、職人の手で一つ一つ丁寧に彫り上げられた逸品です。
重厚な存在感と繊細な彫刻は、単なる装飾を超えた“庭の主役”としての風格を放ちます。
庭全体の印象を一段格上げしたい方や、長く大切に使えるものを求めている方におすすめです。
設置には専門業者の手配が必要なこともありますが、それに見合う価値がしっかりと感じられる灯籠す。
庭に格式と静寂をもたらす、本格石灯籠
御影石を用いた本格的な春日灯籠。
重厚感ある姿と丁寧な彫刻が、和の庭に深みと品格を与えてくれます。
置くだけで空間が引き締まり、庭全体の印象が格段に高まる存在感。
静けさの中に凛とした風格を宿した、本物志向の方にふさわしい逸品です。
▶ 楽天で詳細を見る
春日灯篭の購入前に確認すべき注意点!
- 転倒防止と基礎の作り方
- 運搬・設置時のポイント
- 掃除とメンテナンスの方法
転倒防止と基礎の作り方

春日灯籠の設置において、もっとも重要なポイントのひとつが「転倒防止」です。特に石材の灯籠は重量があり、万が一倒れてしまうと危険なだけでなく、灯籠自体が破損してしまうおそれもあります。しっかりとした基礎を作って設置することで、安全性と美しさの両方を保つことができます。
まず、設置場所の地面が柔らかい場合や傾斜がある場合は、そのまま置くだけでは安定しません。最低でも地面を20〜30cmほど掘り下げ、砕石や砂利を敷いて転圧し、水平を取る作業が必要です。その上にコンクリートを流してしっかりと固めることで、灯籠の基礎として安定します。
市販の灯籠には、竿部分に「芯棒」を通せる構造のものもあり、芯棒を基礎のコンクリートに埋め込むことで、より高い転倒防止効果が得られます。こうした加工が可能かどうかは、購入前に確認しておくと安心です。
また、灯籠は一見すると一体に見えますが、実は複数のパーツ(笠・火袋・中台・竿・基礎石)に分かれていることが多いため、それぞれをズレないように配置・接着する作業も重要です。ズレ防止には、専用の石材用ボンドやコーキング剤を使用すると、強度を保ちながらも見た目を損ねずに済みます。
設置後の見た目だけでなく、長年にわたって安心して庭に置いておけるためにも、基礎づくりは決して手を抜いてはいけない工程です。初心者の方は、必要に応じて石材店や施工業者に相談するのも良い方法でしょう。
運搬・設置時のポイント

春日灯籠は、見た目の美しさだけでなく重量感も大きな魅力のひとつです。しかし、それが同時に「運搬の難しさ」や「設置時の手間」につながっていることを理解しておく必要があります。特に石製の本格灯籠は数十キロ〜100kg以上になることもあり、慎重な作業が求められます。
まず運搬についてですが、一人での持ち運びは基本的にNGです。石は重さ以上に“割れやすさ”があるため、無理に運ぼうとすると破損やケガのリスクがあります。特に火袋や笠の部分は繊細な彫刻が施されている場合も多く、少しの衝撃でも欠けてしまうことがあるため、毛布や緩衝材で丁寧に包んでから運搬するのが安全です。
灯籠はパーツごとに分かれているため、「部品を分解して運び、設置場所で組み立てる」のが一般的です。組み立ての際は、各パーツを載せる向きを間違えないよう、事前に仮置きしてから本設置を行うと失敗を防げます。
また、地面が斜めになっている場合や、不安定な場所に設置する場合は、水平器でしっかりと水平を取ることが大切です。傾いた状態で設置すると、数日〜数週間で倒れてしまうリスクがあります。
庭が狭く、灯籠を運び入れるスペースが限られている場合は、小型の台車やスライダー(滑り台のような運搬板)を使うと、安全かつ効率的に作業できます。それでも不安な場合や、灯籠のサイズが大きい場合は、プロの石材業者に依頼することで、破損や怪我のリスクを減らすことができます。
掃除とメンテナンスの方法
春日灯籠は石材でできているため、基本的には耐久性が高く、風雨にさらされても簡単に劣化することはありません。しかし、長く美しい状態を保つためには、定期的な掃除と簡単なメンテナンスを行うことが大切です。
掃除の頻度としては、年に2〜3回程度が目安です。季節の変わり目や、落ち葉の多い時期などに掃除をすると、庭全体の清潔感も保ちやすくなります。掃除をする際には、まず灯籠の表面に付着したホコリや汚れを、柔らかいブラシや布で優しく払い落とします。強くこすりすぎると、表面の仕上げや彫刻が傷ついてしまうことがあるため注意が必要です。
苔やカビが生えてしまった場合は、薄めた中性洗剤を使い、やわらかいスポンジで軽く擦ると効果的です。ただし、高圧洗浄機などの強い水流は石材を傷める恐れがあるため使用を避けましょう。
火袋の中に雨水やゴミが溜まっていることもあるので、内部の確認も忘れずに行いましょう。特に灯りを灯す予定がある場合、清潔に保つことは安全面からも重要です。
また、冬季には凍結によるひび割れ防止のため、できるだけ水分が残らないようにしておくのが望ましいです。石材は水を吸いやすいため、冷え込みの強い地域では注意が必要です。春日灯籠は、一度設置すれば数十年にわたり使い続けることができるアイテムです。だからこそ、ちょっとした手入れを継続的に行うことが、美しさと安全性を維持する秘訣と言えるでしょう。
春日灯籠で庭を格調高く演出するためのまとめ
- 神社や寺に多く使われてきた由緒ある石灯籠
- 奈良時代から続く歴史と信仰に根ざした灯籠
- 春日大社の回廊や社殿に多く見られることが由来
- 鹿や月などの彫刻に宗教的意味が込められている
- 火袋の窓の向きは庭の視線誘導に大きく関わる
- 庭の設計において構成の“軸”になる存在
- 見せたい面を意識して設置することで印象が変わる
- 視線の終点やアプローチに置くと格式が強調される
- 対角線や非対称配置で奥行きやリズムが生まれる
- 雪見灯籠と比べて縦長で荘厳な印象を与える
- 和モダンな庭にも素材感と直線美で自然に馴染む
- 設置には基礎づくりと転倒防止策が重要となる
- 運搬は分割し丁寧に行い、破損リスクに注意が必要
- メンテナンス次第で数十年使える長寿命の石材製品
- 初心者はサイズ・素材・価格のバランスで選ぶとよい
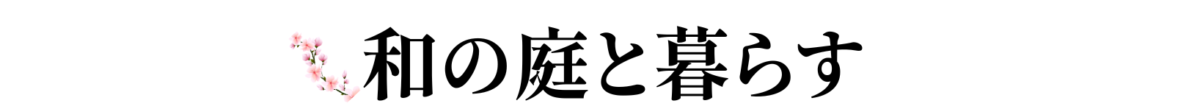


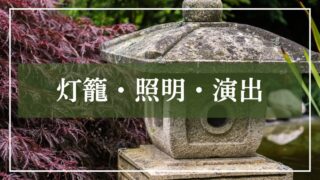
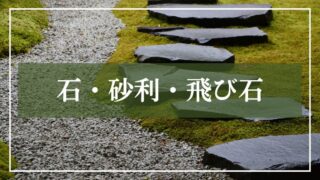


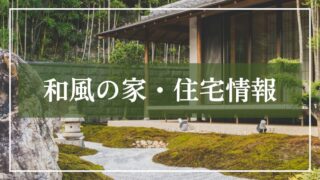
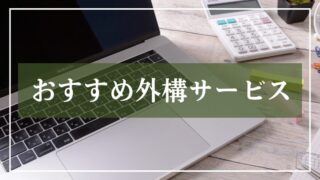






コメント